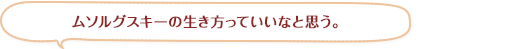らららクラシック
 19世紀のロシアで最も個性的な作曲家といわれるムソルグスキー。
19世紀のロシアで最も個性的な作曲家といわれるムソルグスキー。
彼が残した作品の中でもとりわけユニークな管弦楽曲、交響詩
「はげ山の一夜」。この曲でムソルグスキーは、ロシアならではの
題材でロシアならではの音楽を創り上げることをめざした。
生涯を賭けてロシア音楽の創造に命を賭けた天才の肖像を紹介する。

民間伝承を忠実に再現した音楽

ムソルグスキーが「はげ山の一夜」で描いたのは、夏至の頃に現れる悪魔たちの夜の世界だった。古来ロシアにあった民間伝承や、キリスト教が入ってきてから祝うようになった聖ヨハネの誕生日の祭りなどを題材にして作品をつくりあげた。音楽は夜になって、悪魔のボスの登場し、その号令によって悪魔たちが大集合する様子。集まった悪魔たちが、歌ったり踊ったりする宴会の様子を中心に描く。終盤に朝を知らせる鐘の音が鳴ると悪魔たちの時間は終了。平和な朝が訪れる。といったストーリーになっている。
ロシア・ファーストの音楽を作りたい

ムソルグスキーが生きた19世紀のロシアでは、イタリア、フランス、ドイツの音楽が頻繁に演奏され、ロシアの作品はあまり演奏されていなかった。そんな状況をムソルグスキーは残念に思っていた。もっと残念に感じていたのは、ロシア人の作曲家の作品からロシアの香りがしない場合だった。ムソルグスキーは、ロシア人ならではの音楽を創り上げるには、民間伝承の忠実な再現や農民をはじめとする民衆の姿を描くことだと考えていた。地方貴族で大地主の家に生まれ育ったムソルグスキーが幼い頃、ともに遊んだ農民の子供たちや、民話を語ってくれた乳母への深い愛情を持ち続けていたことも大きな理由だったかもしれない。この曲は1867年に一度発表したが、斬新すぎたのか演奏されることは無かった。その後オペラの中の歌としてリメイクして再発表しようとしたが、今度は彼自身の死によって未完に終わった。
現在、頻繁に演奏されているのは、ムソルグスキーの友人だったリムスキー・コルサコフがオペラ版を編曲した管弦楽曲だ。生前は日の目を見なかった「はげ山の一夜」だが、その後のロシアの歴史をみれば、ムソルグスキーが注目した民衆たちによる社会主義革命が起こるなど、ロシアの民衆の姿を芸術に描くことは歴史を先読みしていたともいえるのだ。