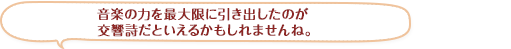らららクラシック
裏には人知れず抱えていた悩みがありました。
この作品をヒットに導いた彼の巧妙な手口とは-。


敏腕プロデューサーの手腕

「ピアノの魔術師」と呼ばれ、人気ピアニストとしてヨーロッパ中を駆け回っていたリスト。しかし次第にピアニストとして喝采を浴びるだけの人生にむなしさを覚え、作曲家として生きることを決意します。客観的に音楽と向き合ううちに芽生えてきた「より広く音楽を世に届けたい」という思い。当時大都市で流行していたオペラや交響曲などを自らピアノ曲に編曲し、各地の演奏会で披露するようになりました。リストのおかげで、原曲が広まったということもしばしば。新しい音楽を次々に紹介する、まさに「敏腕プロデューサー」だったのです。
わかりやすさの追求

ベートーベンが究めた交響曲を進化させようとしのぎを削っていた19世紀。リストは、詩と交響曲を融合させた「交響詩」という新たなジャンルを開拓します。とにかくわかりやすい、聴衆があきない長さでありながら、文学にも劣らない内容を表現する、それがリストの交響詩「レ・プレリュード」。この作品には、生きることは死へのプレリュード、つまり前奏曲であるという詩が添えられています。
リストの壮大な演出!?
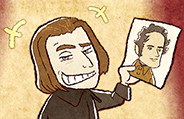
「レ・プレリュード」には当時のフランスを代表する詩人、ラマルティーヌの名前が。 しかし実際、この曲の元になったのは、オートランという詩人による詩。リストは当時、より有名だったラマルティーヌの名前を使うことで、広く伝わりやすい音楽を目指したのです。そのためには、他人の名声をも利用する、巧妙なリストの作戦だったのです。
変幻自在!リストのオーケストレーションの妙

野本さんによれば、この曲には、「主人公」ともいうべき音型があります。この音型は様々に変化し、人間の一生で起こる出来事を象徴的に描きます。ここに、聴くものの想像を駆り立てるリストの技があるのです。